もう迷わない空調負荷計算の基礎から実務までのガイド
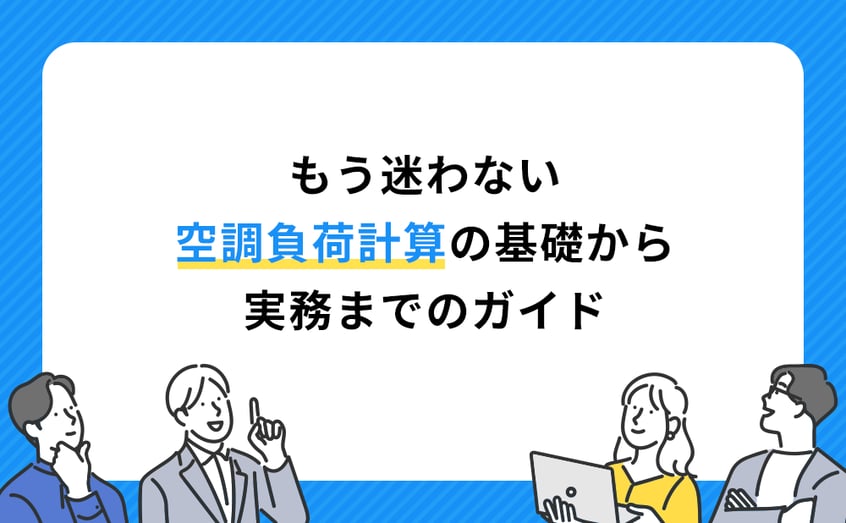
空調負荷計算と換気設計の重要性や空調・換気を最適化する手順などを解説。
空調負荷計算と換気設計の重要性

2025年4月、建築物省エネ法の改正により、すべての新築建築物に省エネ基準の適合が義務化されました。この改正によって、既存の建築物においても、増改築を行った部分は省エネ基準を満たす必要があります。
これは、地球温暖化対策の一環として、日本が掲げる「2050年カーボンニュートラル」や「2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比)」の目標達成に向けた大きな一歩です。エネルギー消費量の約3割を占める建築物分野での取り組み強化が求められており、今回の法改正はその流れを加速するものです。
改正された「建築物省エネ法」によって、新築に限らず、増築・改築においても対象部分に省エネ基準の適合が義務付けられました。建築物の規模や用途(住宅・非住宅)を問わず、省エネ性能の計算結果を提出し、適合性判定を受ける必要があります。
つまり、建物の着工にあたっては、まず省エネ性能を確保することが前提になります。その際、設計者が初期段階で重視すべきポイントのひとつが「空調負荷の計算」と「換気量の算定」です。
これらを適切に見積もることは、設備の容量に過不足がないようにし、イニシャルコスト(初期費用)とランニングコスト(運用費)を最適化するうえで極めて重要です。用途や使用条件に合わせて空調・換気設計を行えば、厚生労働省が推奨する「屋内CO₂濃度基準(1,000ppm以下)」をクリアしやすくなります。
特に近年の建築物は気密性が高く、自然換気だけでは不十分なケースが増えています。建築物のエネルギー消費性能を表すBEI値を低減させるためにも、全熱交換器などの高性能な機械換気設備を活用し、計画的な換気を行うことが必要不可欠です。
省エネ基準を「守るため」だけでなく、「快適で健やかな空間づくり」の観点からも、空調と換気の設計は今後ますます重要になっていくでしょう。
空調機と換気の“両輪”で快適空間を実現
空調機は、室内の空気を循環させながら温度や湿度を調整する設備です。ただし、あくまで「循環」であり、室内の空気を屋外の新鮮な空気と入れ替える“換気”は行っていません。
そのため、人が快適に過ごす環境をつくるには、空調機で空気を整えるだけでなく、換気設備で空気を入れ替えることが不可欠です。特に現代の建物は高気密化が進んでおり、自然換気に頼るだけでは不十分なケースが多くなっています。
入力条件と換気量が左右する計算精度

空調機を設計・選定する上で重要なのが「負荷計算」です。これは、室内の温度を一定に保つために必要な熱量(熱負荷)を、部屋の用途や広さなどに応じて算出し、必要な空調機の能力を割り出す作業です。もし必要以上に能力の高い空調機を導入すれば、設置費用がかさむだけでなく、冷えすぎ・暖まりすぎといった不快さが生まれる可能性もあります。逆に能力が不足すると、「効きが悪い」「常にフル稼働になり電気代が高い」「機器の寿命が縮む」などの問題を引き起こします。
一般家庭では、過ごし方が比較的一定であるため、「◯畳用」といったメーカー表示を参考にすることもできます。しかし、非住宅の建物(たとえば飲食店、オフィス、店舗など)では、空間の使い方が多様であり、より綿密な負荷計算が必要です。
負荷計算を行う上で負荷と換気量を把握することは重要です。
負荷と換気量の目安
空調機の冷房負荷は、建物の用途ごとにおおよその目安があります。
| 建物の用途 | 冷房負荷の目安(W/m²) |
|---|---|
| 一般的なオフィス | 115~170 |
| 商店 | 155~230 |
| 飲食店 | 230~370 |
| 喫茶店・理美容院 | 230~290 |
換気については、建築基準法において「1人あたり20㎥/h(立方メートル毎時)」が必要とされています(※1)。たとえば、在室人数が10人の場合には、最低でも200㎥/hの換気量が必要という計算になります。
必要換気量(㎥/h)=「20(㎥/h・人)」×「部屋の床面積(㎡)」÷「1人あたりの占有面積(㎡)」
空調負荷に大きく影響する換気量も正確に把握し、計画段階からしっかり設計することが、省エネ性能だけでなく、快適な室内環境の実現にも直結します。
また、厚生労働省は感染症予防のため、1人あたりの必要換気量に「30(㎥/h)」を推奨(※2)しているので、該当箇所の数字を置き換えることで計算できます。
※1 参照:日本環境感染学会
http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/20220128-iryo-seminar_1.pdf
※2 参照:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策分科会
https://www.mhlw.go.jp/content/001020788.pdf
負荷計算を行う上では以下のような要素が精度を左右するため、十分整理しておくことが重要です。
・外気温や日射の影響
・厨房機器・照明・電子機器などの発熱量
・在室人数や動きの多さ
・ドアの開閉頻度(路面店ではドア開放も考慮)
・必要な換気量(*空気の清浄度を保つため)
空調機単体では快適性も省エネ性も十分に実現できません。換気設計との連動が、建物全体の空調計画の質を左右します。
効率よく“換気”するための鍵は「全熱交換器」です。
室内の汚れた空気を効率的に外に排出するには、機械換気システムの導入が効果的です。ただし、熱交換をしない一般的な換気扇では空調との相性に課題があります。たとえば、夏は冷房で冷えた空気が、冬は暖房で温めた空気がそのまま外へ排出されてしまい、空調効率が大きく低下します。
この課題を解決するのが、「全熱交換器」と呼ばれる設備です。
全熱交換器は、室内の排気と屋外からの給気を同時に1台で行う換気装置で、内部に搭載された熱交換素子によって、空気の温度や湿度の“熱エネルギー”を回収・再利用することができます。たとえば夏であれば、冷房で冷えた空気が排出される際に、その冷気のエネルギーを給気側に移すことで、屋外から取り入れる空気を冷やして室温との差を小さく保ちます。冬も同様に、暖房で温めた空気の熱を再利用しながら外気を取り込むことが可能です。
このように、室温を極力保ったまま換気ができるため、空調負荷を軽減し、光熱費の削減にもつながります。
空調・換気を同時に最適化する手順

空調は換気の影響を大きく受けます。空調機の能力の過不足を避けるために、空調設備設計の際には換気もセットで設計・最適化することが重要です。
以下に、空調設備の選定における基本的な流れをご紹介します。
ヒアリング
企画段階でのヒアリング不足や情報の聞き漏れは、施工や点検といった後工程のやり直しにつながる大きなリスクとなります。
企画段階での把握が必要な設計条件の根幹となる情報を正確に得ることが重要です。
負荷計算
建物用途や面積、在室人数、設備の発熱量、換気量などをもとに、冷暖房の負荷を数値で見積もります。負荷計算は、空調容量の過不足を防ぎ、設備の適正選定に不可欠なステップです。
機器台数の決定
負荷計算の結果をもとに、空調機の機種選定(機種、台数)をします。過剰な台数による無駄なコストや、逆に不足による性能不良を避けるためにも、精度の高い計算が求められます。
BIMの活用で空調・換気設計が進化
近年では、建築の設計・施工・維持管理のすべての段階において、「BIM(Building Information Modeling)」の導入が進んでいます。BIMとは、建物の形状や設備情報を3Dモデルとして一元管理する仕組みで、設計者・施工者・発注者間の情報共有や意思決定をスムーズにします。
空調や換気設備の設計においても、BIMや設備用CADの3Dデータを活用して負荷計算を行い、設備容量や台数を高精度でシミュレーションする手法が一般化しつつあります。これにより、より合理的で効率のよい設備設計が可能になり、省エネ性や快適性の両立を実現することができます。
快適性と省エネの両立をめざして
これからの建築には、省エネ性能の確保と同時に、人が心地よく過ごせる空間づくりが求められています。空調と換気はその両輪であり、設計初期から一体的に検討することが非常に重要です。
制度改正により、省エネ基準の適合がすべての新築建築物で義務化された今、設備設計の質が、建物の価値そのものに直結します。
失敗事例に学ぶ/空調機の負荷計算で避けたい落とし穴

ここまで、空調設備設計における基本的な考え方や手順をご紹介してきましたが、実際の現場では「負荷計算の誤りや見落とし」によって、大きな問題が発生するケースも少なくありません。
たとえば、必要以上に能力の高い空調機を選定してしまえば、初期コストや運用コストが想定以上に膨らむ結果となります。逆に、能力が不足していれば冷暖房の効きが悪くなり、空間の快適性が損なわれるだけでなく、換気が十分に行われず、室内環境が悪化することで健康リスクが高まる可能性も出てきます。
【事例】在室人数の見積もりミスで追加工事に
あるオフィスビルでは、空調設備設計時に在室人数を過小に見積り、換気設備設計とは別で対応したことが原因で、設置された空調機の能力が実際の使用環境に対して不足してしまうというトラブルが発生しました。
特に夏場には、冷房が十分に効かず、従業員から「暑くて集中できない」といった声が上がるように。最終的には、空調機器やダクトの追加工事が必要となり、数百万円規模の想定外のコストが発生しました。
このような事例からも分かるように、「空調負荷の見積もりは、実際の使用状況を正確に反映することが非常に重要」です。とくに、オフィスや商業施設など人の出入りが多い建物では、在室人数・使用設備・運用時間などを細かく把握し、慎重に計算を行う必要があります。
全熱交換器が空調負荷に与える効果
空調負荷の計算において、もう一つ見落としがちなのが「全熱交換器の導入有無による影響」です。前述の通り、全熱交換器は排気に含まれる熱エネルギーを給気側に移すことで、室温の維持と省エネを両立させる役割を果たします。
日本冷凍空調工業会が公表したデータ(※3)によれば、床面積418㎡、在籍者数44名のオフィスに全熱交換器を導入したところ、次のような効果が確認されました。
夏期:空調機の消費電力量が最大20%削減
冬期:同最大30%削減
特に冬期の削減効果が高い理由は、室温と外気温の差が夏よりも大きいため、熱エネルギーの回収効果がより顕著になるためです。
※3 参照:日本冷凍空調工業会
https://www.jraia.or.jp/product/exchanger/result.html
日本キヤリアの省エネ製品のご紹介
空調・換気の効率化がますます重要になる中、日本キヤリアでは、省エネと快適性を両立する製品ラインアップを展開しています。
そのひとつが、全熱交換ユニット「ヒートクルエアー®」です。空調負荷を大きく軽減し、使用しなかった場合と比べて空調・換気設備を合わせた年間消費電力を最大約33%削減(※4)できるという試算結果が得られています。また、別売りのCO₂・PM2.5センサーと連動させることで、室内の空気質(CO₂濃度やPM2.5濃度)に応じて換気量を自動制御。無駄な換気を抑えながら、効率的な空気環境の維持が可能になります。空調機との連動運転にも対応しており、1台のリモコンで換気と空調を一括操作できる点も、操作性と管理性に優れた特長です。
さらに、当社では省エネ性能の高い店舗・オフィス用カスタムエアコンやビル用マルチ空調システム「スーパーマルチu®シリーズ」なども取り揃えています。
空調機の負荷計算には換気の影響を考慮することが重要です。高機能な換気設備を導入することで室内の空気を清潔に保ちながら、空調負荷を抑えることが可能になります。
建物の規模や用途に合わせて、最適な空調・換気ソリューションをご提案いたします。ぜひ、日本キヤリアへお気軽にご相談ください。
※4 消費電力量削減率は、当社による試算に基づいたものであり、使用条件や地域によって異なります。
札幌・仙台・東京における試算では、空調と換気を合わせた年間の消費電力量が、それぞれ最大で札幌:33%、仙台:28%、東京:27%削減される結果が得られています。
<算出条件>
地区:札幌、仙台、東京
暖房期間:
札幌:10/18~5/1
仙台:11/19~4/17
東京:12/3~3/15
冷房期間:
札幌:6/22~9/20
仙台:4/30~10/6
東京:4/19~11/11
空調設定:
暖房時:22℃、相対湿度50%
冷房時:26℃、相対湿度50%
運転時間:8時~20時(12時間)
用途:事務所
床面積:55㎡
空調方式:
東京・仙台:ヒートポンプエアコン P112形(APF 6.3)
札幌:ヒートポンプエアコンP112形(暖太郎)(APF 6.2)
換気機器:
全熱交換器:VN-UM350RW(風量350㎥/h、機外静圧100Pa時)
非熱交換換気:DVS-40SUK + DVS-40SSUK(風量350㎥/h時)
外気温:JIS B8616:2015 に規定されたデータを使用





