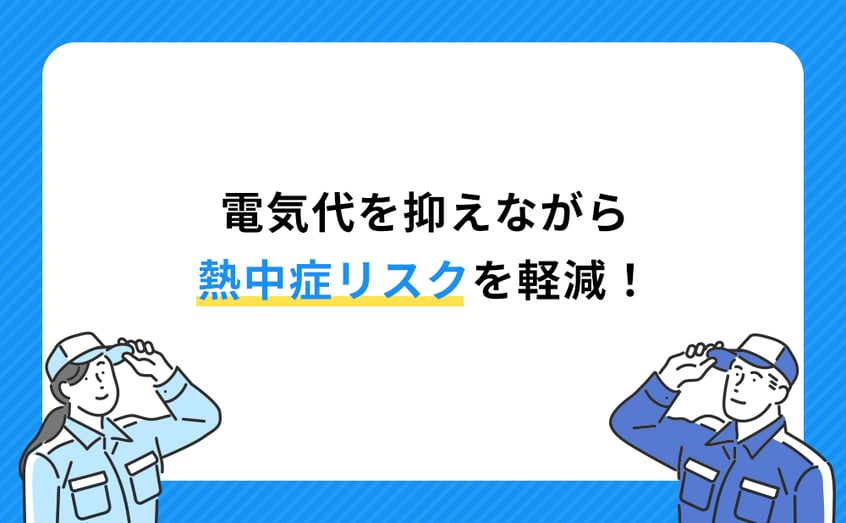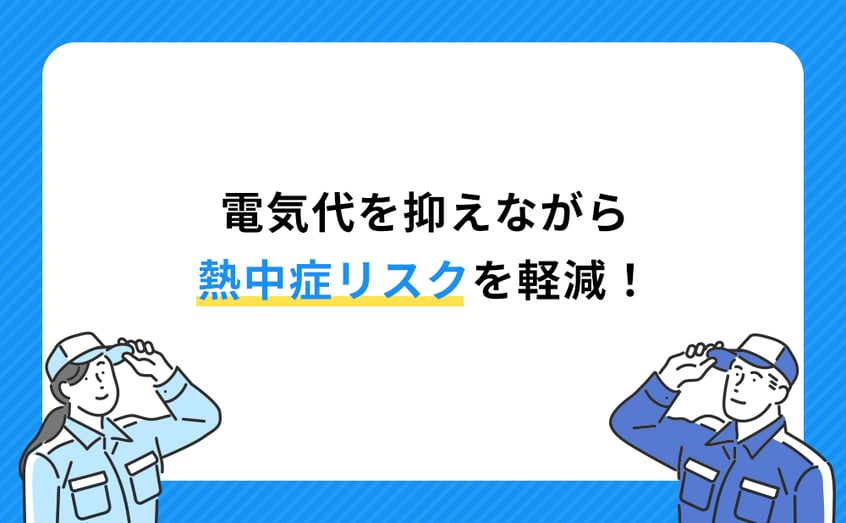近年高まっている暑熱リスクの現状

近年の外気温度上昇傾向により、特に工場や倉庫といった広い空間の中で人口密度が低く作業者の位置が不特定となる建物用途において、室内全体の空調を行うことは空調設備の増設が必要となり投資費用が大きくなります。さらには、作業者不在のエリアへの空調も行うことになるため、消費電力が増加し導入することが難しい傾向があります。このことにより、工場や倉庫といった室内での作業に対して十分な空調ができず、人体発熱や機械発熱などによって温度や湿度が上昇し作業者が熱中症になる事故が増えています。
2022年から2024年にかけて、屋外を含む作業所で、3年連続で熱中症による死亡災害が30人以上となりました。こうした事態を受け、2025年6月から労働安全衛生規則が改正され、事業者には熱中症を早期発見しその後の重篤化を防止するための「体制整備」「手順作成」「関係者への通知」が義務付けられました。
規制の対象となるのは、「暑さ指数(WBGT)が28℃以上または気温が31℃以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」です。
暑さ指数(WBGT)とは、気温だけでなく、湿度や日射、建物や地面からの輻射熱などを考慮して算出される指標のことで、熱中症リスクの判断や予防に活用されています。
熱中症対策の義務化で具体的に求められる対応には、以下のものが挙げられます。
・熱中症の自覚がある作業者や熱中症の恐れがある作業者を見つけた人がそれを報告する体制の整備
・緊急連絡網の整備および搬送先の連絡先・所在地の周知
・熱中症の恐れがある作業者の重篤化を防ぐために、現場で行うべき処置手順の作成や周知
熱中症対策の義務化に関わらず、現場作業者に安全な環境で働いてもらうことは必須です。その解決策の一つが高効率な空調機器への更新です。電気やガスなどのエネルギーコストが高騰する中、安全な作業環境づくりとエネルギーコストの抑制のために空調機器の更新について検討してみてください。
最新空調の省エネ性能の進化で電気代を削減

熱中症対策と電気代抑制を両立させるためには、消費電力が抑えられる高効率な空調機器を導入することが近道です。最新のビル用マルチエアコンやカスタムエアコンは、インバータ圧縮機と高性能熱交換器の採用などにより、消費電力量を大きく抑制することが可能です。
なお、インバータ圧縮機は、冷暖房を行うための「圧縮機(コンプレッサー)」を動かすモーターの回転数を、室温の変化や必要な出力に応じて細かく調整できる仕組みです。これにより、冷暖房の出力を無駄なく制御でき、従来の一定速タイプと比べて消費電力を大きく抑えることが可能です。特に真夏・真冬以外の中間期には、軽い負荷での運転が多くなるため、インバータ機器の高い省エネ性が効果を発揮します。
省エネ性の高い最新の空調機器であれば、暑さを我慢せずに適切に稼働させても、年間の電気料金を抑えられるケースが多く、熱中症対策とコスト削減を同時に実現できます。業務用空調の省エネ性能は年々進化しています。10年前に導入した空調の調子が悪い、という場合には修理を繰り返すよりも最新機種に入れ換えた方が、ランニングコストが抑えられ、投資回収の期間が短くなることも少なくありません。
局所暑熱を抑える空調設計ポイントの極意

敷地が広く天井の高い倉庫や工場では、高効率な空調機器への更新だけでは現場の快適性が担保できない場合があります。作業者の熱中症予防としては、空間全体を均一に涼しくすることよりも、作業員がいる場所に的確に冷たい空気を届けることの方が重要です。作業者がいる場所周辺に重点的に冷たい風を送ることで、作業場全体の室温を過剰に下げる必要がなくなるため、節電にもつながります。
工場や倉庫で快適な作業環境を整えるためには、空調機器の更新や追加と同時に、空調機器の吹き出し口の配置や風量バランスも考慮する必要があります。「誰が」「いつ」「どこで」作業するのかを洗い出すことで、無駄のないより効率的な空調設計が可能になります。
例えば、必要な区画だけにきめ細かく冷風を送れるよう、室内機ごとに電源の切り替えや風向・風量の調節ができる仕様の機器を導入することで、無駄のない空調運用に役立ちます。
補助金活用とコスト見える化で導入ハードルを下げる

高効率な空調機器を導入する際には、機器本体や設置費用といった初期コストが気になるところです。国や自治体では、2050年カーボンニュートラル実現に向け、省エネ性の高い空調機器の導入に対して補助金制度を設けています。これを活用すれば、導入時の負担を大きく軽減できる可能性があります。
とはいえ、補助金を利用しても、単年で見れば大きな費用負担になります。企業経営においては初期費用の大きさだけでなく、その後のランニングコストも含めて設備導入の是非を判断することが求められます。その際にヒントとなるのが、新しく導入を検討している空調機器の「ライフサイクルコスト」です。
ライフサイクルコストとは、建物や設備、製品などの資産を取得してから廃棄するまでの全期間に発生する総コストのことを指します。購入費用だけでなく、計画・設計・設置にかかる費用、運用に伴う光熱費やメンテナンス費用、修理・更新・廃棄に必要な費用までを含みます。
空調機器においても同様で、高効率機器を導入すれば、こうしたトータルのコストを抑えられる可能性があります。
導入前にライフサイクルコストを算出しておけば、暑熱対策に必要な投資を中長期的に見通すことができます。空調機器を新設・増設する際には、補助金制度の活用とあわせて、ライフサイクルコストの検討も忘れずに行うことがポイントです。
日本キヤリアの製品を紹介
日本キヤリアは、省エネ性能が高く、電気代抑制にも繋がる製品を多数ご用意しております。
半屋外や倉庫、工場、体育館といった広い空間では、暑さの感じ方に差が出やすく、場所によって快適性にばらつきが生じがちです。こうした環境では、必要な場所にだけ冷風を届けるスポット空調や、一定のエリアを対象とするゾーン空調が効果的です。
「FLEXAIR®」は、こうした暑熱環境に対応し、効率よく冷風を届けることで、熱中症リスクの軽減に貢献します。
また、「シングルエースu™」シリーズは室内・室外ユニット一体形で、室内に機器を設置する必要がない省スペース設計です。
設置場所や空間の広さに応じて適切な機種を選べるラインアップがそろっており、熱中症対策としても効果的なスポット・ゾーン空調にも活用しやすい製品です。
日本キヤリアでは、こうした製品の特性を活かし、現場ごとの課題に応じた空調更新のご提案も行っています。局所暑熱やエネルギー効率に関するお悩みがありましたら、ぜひご相談ください。