トラブル事例から考える『失敗しない空調メンテナンス』 ―故障要因と対策チェックリスト
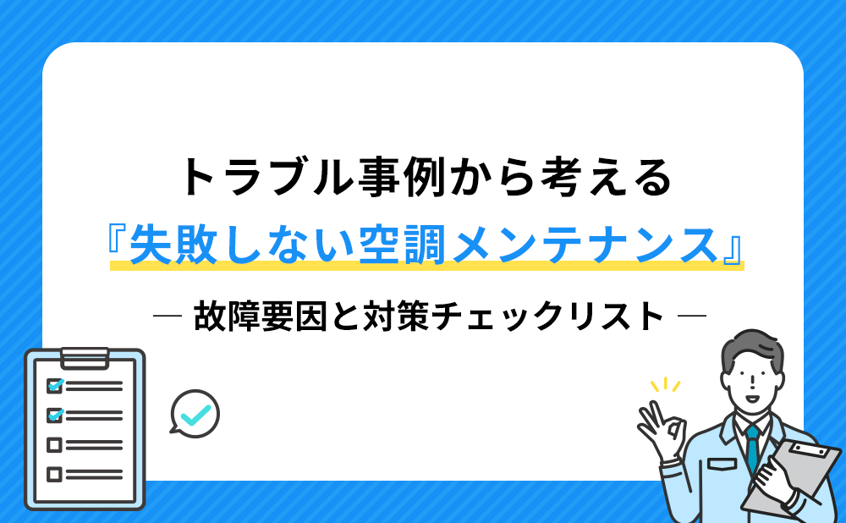
近年高まる暑熱リスクの現状や局所暑熱を抑える空調設計のポイントなどを解説。
よくあるトラブル事例と現場の声

「猛暑日になるとエアコンがしっかり効かない」「天井から水が垂れてくる」「室外機から異音がする」。これらは設備工事店やビル管理会社に寄せられる代表的な空調トラブルの声です。
空調は季節によっては長時間稼働が必要になるため、万一トラブルや故障が発生すると、テナントからの苦情対応、修理費用の負担、一時的な営業停止など、ビル管理会社やオーナーにとって大きな経済的損失となります。些細な不具合であっても、放置することで故障や交換につながる恐れもあるため、定期的な点検は非常に重要です。
また、業務用空調には冷媒として「代替フロン」が用いられています。これは、オゾン層を破壊しないものの、大気中に放出されるとCO₂の数十倍以上の温室効果があります(※)。このことから、代替フロンを使用するユーザーには、それを排出させないための適切な管理が求められています。これを定めているのが「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)です。
※参照:経済産業省製造産業局オゾン層保護等推進室
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/kagaku_busshitsu/pdf/008_04_00.pdf
フロン排出抑制法では、すべての第一種特定製品に対して『簡易点検』を3カ月に1回以上行うことが定められており、安全に行える場合は専門業者でなく、テナントやビルの設備管理者などが実施しても問題ありません。簡易点検では、機器の振動や異音、熱交換器の腐食や霜付きの有無を目視で確認します。
さらに、簡易点検に加えて、圧縮機の定格出力が7.5kW以上の機器については、専門業者などによる『定期点検』も定められています。
| 点検の種類 | 点検者 | 点検方法 | 圧縮機電動機 定格出力 |
点検頻度 |
|---|---|---|---|---|
| 簡易点検 |
誰でも(委託可) |
目視 | 出力を問わず実施 | 3カ月に1回以上 |
| 定期点検 | 専門業者など | 専用の機器を使用 | 7.5kW以上 50kW未満 |
3年に1回以上 |
| 50kW以上 | 1年に1回以上 |
簡易点検や定期点検を怠った場合には以下のような罰則(※)が設けられています。
・算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合、10万円以下の過料
・機器の使用・廃棄等に関する義務について都道府県知事の命令に違反した場合、
・フロン類をみだりに放出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
※参照:フロン排出抑制機構
https://furon.org/staff/guide-penalty-2/
点検を怠ったことで建物の水漏れなどの被害が生じた場合、保険の適用外となる恐れもあります。経営リスクの観点からも「定期的な空調メンテナンス」を行うことが重要です。
故障を招く三大要因と見抜き方

「フィルタの目詰まり」「熱交換器の汚れ」「冷媒不足」は、空調の故障の三大要因とされています。これらは日常的な点検で早期に発見できる可能性があります。目視では確認が難しいものについては、専門業者に依頼することをおすすめします。
●フィルタの目詰まり
フィルタの目詰まりが起こると、空調機から十分に風が吹き出せず、空調効率が低下します。これにより、室内温度が設定温度になるまでの時間やフル稼働する時間が長くなり、空調機への負担が蓄積して故障しやすくなります。また、消費電力の増加にもつながってしまいます。フィルタの目詰まりは目視によるチェックや、圧力計を用いた静圧測定などで確認できます。
●熱交換器の汚れ
熱交換器は空内の空気を暖めたり冷やしたりする重要な部分です。汚れが溜まると熱交換効率が悪くなり冷房能力の低下や霜付きなどにつながります。空調機の吹き出し口と吸い込み口の温度計測などの方法で、熱交換器の状態を確認することができます。
●冷媒の不足(漏えい)
空調に欠かせない冷媒(代替フロン)は、空調を運転させることで少しずつ減っていくというものではありません。空調が効かない、冷房にしているのに暖かい空気が出るといった場合には、空調機の配管の老朽化などにより、そこから冷媒が漏れて不足している可能性があります。
こうした不具合を早期に発見するには、点検時の記録をしっかり保管しておくことが重要です。点検ごとの数値を残しておけば、経年劣化や故障による異常値などの分析が可能になり、トラブルの防止に役立ちます。
また、空調機の不具合は、そのまま空調効率の低下を招きます。早めに対応できる体制を整えておくことで、トラブルを防ぐだけでなく、省エネ効果も期待できます。
空調トラブルを防ぐ!夏前・夏後にやっておきたい空調メンテナンスチェックリスト

本格的に空調を稼働させる夏の前と、酷暑を乗り切った夏の終わり頃は、メンテナンスに最適なタイミングです。冷房をしっかり効かせて快適に夏を過ごすため、また暖房シーズンに備える意味でも、この2つの時期にメンテナンスを行うことをおすすめします。実施すべきメンテナンス項目は以下の通りです。メンテナンスは専門的な作業を伴うものもあるため、必要に応じて専門業者への依頼もご検討ください。
1.フィルタの洗浄
カビやホコリなどで目詰まりを起こしているフィルタを取り外し、洗浄します。ホコリは掃除機で吸いとり、目詰まりがひどい場合には水洗いを行います。洗浄後はしっかりと水気をふき取り、日陰で完全に乾かしてから再装着します。
2.熱交換器の高圧洗浄
熱交換器は、冷暖房能力に大きく関わる部位です。フィンやファンに付着したカビ・ホコリ・油汚れなどを、高圧水流で除去します。空調内部のカビやホコリが除去されれば、嫌なニオイの予防にもなります。
3.ドレン配管・ドレンパンのバイオフィルム洗浄
バイオフィルムとは微生物が集まってできる膜のような汚れです。空調機器の内部で発生する結露水を受け止めるドレンパンや、結露水を排出するためのドレン配管内にバイオフィルムが発生すると、排水不良や水漏れ、空調効率の低下などにつながるため、徹底的に洗浄しましょう。
4.冷媒漏えい検査
冷媒が漏れていると、冷暖房の効きが悪くなり、空調本来の性能が発揮できなくなります。漏えい検査は、空調の安定稼働のために欠かせない重要なメンテナンス項目です。
なお、冷媒が漏れている状態で、防止措置や修理を行わずに新たな冷媒を充填することは、原則として禁止されています。異常が見られた場合は、可能な限り速やかに漏えい箇所を特定し、適切な措置を行う必要があります。
5.ベルト交換・軸受給脂
空調機器にはファンモーターから送風機に動力を伝えるためにベルトが用いられているものがあります。ベルトは消耗品であり、損傷や磨耗が激しい場合は交換が必要です。
また、ファンやモーターなどの回転する部品を支える軸受は、潤滑性がなければ磨耗スピードが上がり、振動や異音、故障につながることがあります。メンテナンスでは状況を見て給脂を行います。
上記のような項目を行えば、冬季の暖房トラブルや翌夏の冷房障害を未然に防げます。
失敗しない保守計画―費用と人員の最適化

空調は導入後、どのように運用・保守を行うかによって、その後のトータルコストが大きく変わってきます。年間の保守計画は四半期ごとに区切り、それぞれの中で稼働負荷に応じた点検頻度や重要項目を設定することでムダのない効率的な保守が可能になります。全てのフェーズで同じように点検するのではなく、夏期直前には冷房能力の確認を重点項目に設定するなど、環境に応じた点検を実施していきましょう。
空調保守については、費用や人員の最適化も検討が必要な項目です。例えば、遠隔監視システムを活用すれば夜間であっても温度や圧力の異常を自動で感知・通知ができるので、夜間要員の負担を軽減することで保守費用の抑制にもつながります。
日本キヤリアの製品をご紹介
空調メンテナンスは簡単にでもこまめに行うことで、本来の運転性能を保ちやすくなり、機器の長寿命化にもつながります。
日本キヤリアでは、省エネ性とメンテナンス性を両立した業務用空調機器を多数ご用意しています。
例えば、店舗・オフィス用カスタムエアコン「スーパーパワーエコゴールド®」の室内ユニットには、冷房運転中の結露水で熱交換器の汚れやカビを洗い流す「アクア樹脂コーティング」、冷房運転停止後に熱交換器のカビの発生を抑える「乾燥運転」、ドレン水に含まれる菌を除菌する「UV-C照射」機能などを搭載した機種があり、メンテナンス負担の軽減に貢献します。ぜひお気軽にお問い合わせください。



